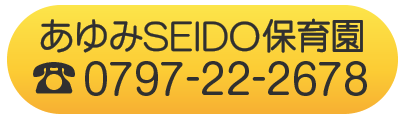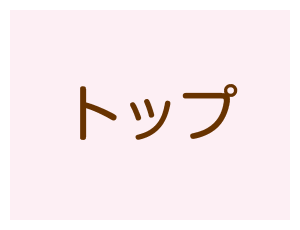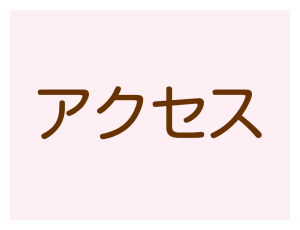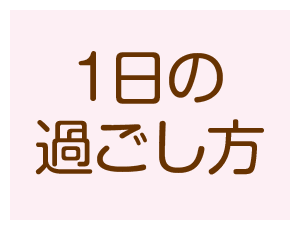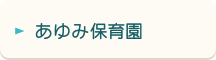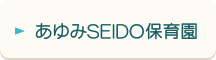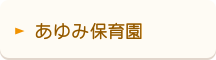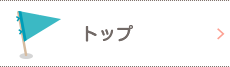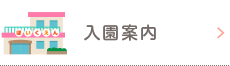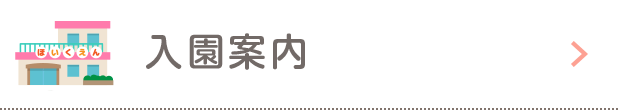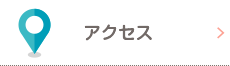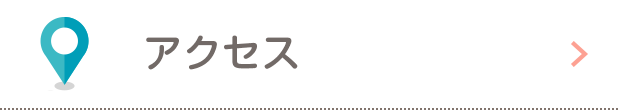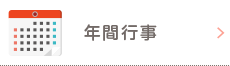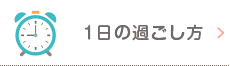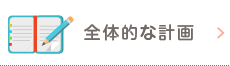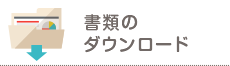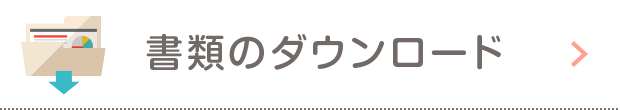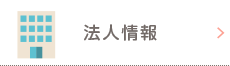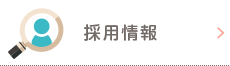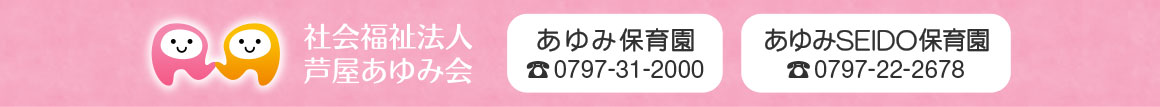あゆみSEIDO保育園の様子
こいのぼりたち

こどもの日を前に子どもたちが「やねよ~り~た~か~い、こいの~ぼ~り~・・・」と歌って、日に日に上手になっています。それに合わせて、園内に飾られたこいのぼりたちが、揺らいでいるように見えます。
今年も子どもたちが元気なこいのぼりをたくさん作ってくれました。
防災訓練をしました

年度の初めに2歳児さんを対象に防災訓練をしました。
地震がら来たらどうするのか、という紙芝居を見て、カブトムシのポーズ。そして防災頭巾をかぶってみました。
やりたくない、と「見学」している子どももいましたが、真剣にトライしている子どももいました。それぞれの対応が面白かったです。
これからまた1年、職員もしっかり訓練を重ねて「いざ」という時に備えておきたいと思っています。
収穫も始まってます

今年度初めての収穫が始まっています。スナップエンドウ。
冬の寒さを生き延びた苗、頑張って大きくなって実をつけました。子どもたちはすでに試食済みです!
2025年度がはじまりました!

園庭の、近隣の 花々が一斉にほころんで、新しい年の始まりを祝ってくれています!
ことしも元気な子どもたちと一緒に過ごしていきます!
定員はまだ空いています
興味のある方はぜひ見学に来てください!
お別れ会でした

1年の最後の行事、お別れ会をしました。
内外が写真と飾りでいっぱいになり、華やかになりました。
あゆみSE IDO保育園から巣立っていく子どもたちがずっと元気にすくすく育ちますように!
ある雨の日です

少し雨の日が続きました。
「おべんとうバス」を演じることにはまっている2歳児さんが、みんなに演じてみせてくれました。何回かやるだけですっかりセリフもナレーションも覚えてしまい、とっても上手でした!
これは先月のクラフト会で先生がご家族のみんなの前で演じたもの。それから2歳児さんはすっかりはまってくれました。
クラフト会
弊園では、2月にクラフト会という「親子で一緒に楽しむ」ことを目的に、イベントをしています。
今回のクラフト会は、キャンバス地の手提げの袋に絵を描く、というものでした。
布の絵具を使うので、服などが汚れてしまうのでは、と心配はしましたが、みなさんの楽しい様子にほっとしました。
他の保育園に行かれているご兄弟の参加もありましたが.それぞれ熱心に描いていましたよ。
ひな祭り

ひな祭りの準備が進みます。
これから子どもたちのかわいい製作が出来上がってきます♡
大根とカブの収穫

園庭のプランターで育てていた大根とカブの収穫をしてくれました。
日当たりも限られた中、よく育ってくれたと思います。
きれいな大根とカブ、園でもいただきますね。
節分、豆まき

今年は節分が日曜日に当たるため、園では金曜日に豆まきをしました。
毎年活躍していた怖い鬼さんの登場を今年は封印してみました。
豆まきのペープサートのお話を先生から聞いて、気分の盛り上がった2歳児さん。支度をして鬼に変身!
可愛い鬼たちに、みんながほっこりしていました。0歳児も今年は歌や踊りの笑顔の節分を楽しんだようです。
その後、ダンボール鬼への豆まきも頑張っていましたよ。
⭐︎節分メニュー⭐︎

今日は豆まき会だったので、
給食も節分仕様でした♪
・おにおにライス
・ブロッコリーの土佐和え
・豆腐のお味噌汁
・いちご大福風蒸しパン
・バナナ
おにおにライスは、チキンライスで
鬼の顔を、ブロッコリーの土佐和えで
髪の毛に見立てました。
こども達も、「おにだー!!!」といいながら
楽しそうに食べていました^^
市役所(北館)の展示コーナーでポスター展示してます!

現在、市役所の北館の展示コーナーで芦屋市の私立保育園・認定こども園・小規模保育所19園のポスターを展示しています。各保育園でどんなことをしているのか、ということが見てもらえると思います。展示期間は31日までなので、興味のある方は見に行ってくださいね。
明けましておめでとうございます!
年が明け、保育園はすでに通常通り始まりました。
子どもたちの製作が園を華やかにしてくれています。
今年もたくさんの笑顔に出会えることを楽しみに願っています。
子どもたちとの初詣を10日に予定しています。
⭐︎お正月メニュー⭐︎

お正月なので、今日の給食はお正月仕様でした!
・松風焼き
・紅白なます
・そうめん入りすまし汁
・鏡餅風おにぎり
・田作り
そうめん入りのおすましは、いつも人気です♪
松風焼きもモリモリ食べていました^^
鏡餅風おにぎりは、みかんに見たてた人参
とブロッコリーがちょこんとのっています♡
明けましておめでとうございます!

年が明け、保育園はすでに通常通り始まりました。
子どもたちの製作が園を華やかにしてくれています。
今年もたくさんの笑顔に出会えることを楽しみに願っています。
子どもたちとの初詣を10日に予定しています。